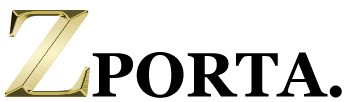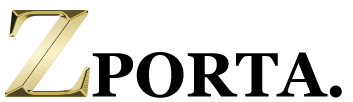オンラインレッスンが楽しくなる!講師の10のコツ
No.1
毎日出席(オンライン)しよう
もちろん、物理的に
教室に行けば良いというわけではありません。
様々な情報の飛び交う
インターネットの世界上で生徒を得るには、
“常に自分の存在をアピール”
しなければなりません。
方法はたくさんありますが
まずは、
「様々な通信手段を活用し、
必要に応じて毎日、随時確実に受付を開けておく」
必要があります。
例として
SNS・ディスカッション掲示板・メール・サイトのお知らせ
、フォーラム(共通テーマの集会所サイトなど)
など、
毎日オンラインで出席する方法は
山のようにあります。
この時、
受講したい人(受講者)が
「いつ・どうやって参加できるのか」の
明確なガイドラインを設定することを忘れないでください。
No.2
興味・関心を引き続ける
オンライン授業は
物理的な教室を持つ授業と違い
しばしば“自由な雰囲気”を感じることが多いでしょう。
そのため、
講師は生徒の興味・関心を引き続ける必要があります。
「授業を受けた後、どうなっていたいか」など
何かわかりやすい目標を設定することも非常に有効です。
受講者に
明確な期待を持たせる必要があります。
そしてこの期待には、
受講後のフィードバック(評価システム)や
コミュニケーションの頻度などの
システムの部分から
講師としての振る舞いや、
受講者に要求されることまで
コース全体を通して継続して提示することも含まれています。

No.3
受講者に‟宿題”を出す
心理学教授のビル・ペルツは、
「効果的なオンライン教育の原則」という論文の中で
「学生がコンテンツに没頭する時間が多ければ多いほど、
より多くのことを学べる」
と論じました。
正しく、
学習の意義として
「受講者がそのコンテンツに触れる機会を作ること」が重要ですよね!
授業を行っていない時間帯にも
「受講者がテーマや他の受講者と交流する機会」
を十分に確保するために、
・リソースを見つけての話し合い
・課題の自己評価
・オンライン集会所での受講者主導のディスカッション
などを
企画してみるのも良いかもしれません!
No.4
グループディスカッションできる環境をつくる
オンライン講座では、
オンラインでいること=教室にいること
と同義になります。
受講者同士で意見を言いあったり、
同じ講座の生徒と一緒に協力したりできるように
クラスの中にグループを作成し、
一般討論の場として議論することを奨励しましょう!
様々な対話形式を使用することで、
コース教材があらゆる学習タイプに対応し、
生徒が活躍できるようになります。
講座が動画形式であれば、
授業中のチャットシステムや
コメントを残せるようにするのも良いでしょう。
傍観者として学ぶ受講者もいれば、
この種のコミュニケーションに積極的に参加することで
大きな利益を感じる学生もいます。
No.5
書く前・話す前にもう一度考えよう
これは講師だけではなく
全ての受講者に
「あらかじめ注意喚起しておくべき原則」ともいえるでしょう。
言葉は、いつの時代も
オンライン/対面式に関わらず、
常に
解釈の違いや捉え方の誤解を生じさせる危険を孕んでいます。
発言の前に今一度、よく考えられているか
もう一度見直す癖をつけてください。
例えば
課題や評価に対する回答を作成する際には、
「シンプル」「明確」「丁寧なトーン」
を使用するのが最適です。
“回答の内容=生徒が行う必要のある課題” であれば、
解釈の余地を残す必要はありませんね!
No.6
生徒からフィーバックを受けよう
講座が
第二回、第三回に差し掛かったあたりで
受講者より
授業のフィードバックや
改善が必要な部分に対してのリクエストをしてもらいましょう。
やや形式的な口調で行うことをお勧めします。
掲示板やグループディスカッションの場などに
何か投稿して、
どんな反応が出るのか確認してみてください。
No.7
個人面談をしよう
No.4のグループコミュニケーションと同じくらい
一人ひとりと個別に話す機会を設けることが重要です。
オンライン教室で学習している受講者は
対面式の教室で学習している場合に比べ
孤独を感じやすい傾向にあります。
それをケアできるかできないか、
あなた次第で
継続率や満足度が大きな差が出ることでしょう。
とはいえ、
大きな手間をかける必要はありません。
方法は簡単です。
例えば、
・掲示板への返信
・1人の生徒だけに宛てたメールの個別対応
などは取り掛かりやすいですよね!
コースの開始時に、
予め最良のコミュニケーション方法を
検討しておく必要がありますが、
私用の連絡先や
個人情報の詳細は
決して受講者に教えないよう、十分注意が必要です。
No.8
個人目標やグループの課題を活用しよう
受講者の個人目標とグループの課題の
共通点・協力できる点を見つけましょう。
個人とグループの目標がうまく組み合わさると
オンライン学習の成功にぐっと近づきます。
様々な学習スタイルを提供することで
学習能力自体を高め、
双方の成果の重要性を教えることができます。
No.9
アクセスしやすいリソース(資料)を使用する
オンライン講座の強みとして
受講者が‟受講中は常にオンライン”で
あるため
オンラインリソースにすぐにアクセスできます。
デジタル出版物やニュースサイト、
オンラインビデオなど、
関連性が高くアクセスしやすい
最新のリソースを利用できることで
教科書などで得る古い情報を参照する場合に比べ
はるかに積極的に
学習できるようになるでしょう。
可能な限り
スマホやモバイル端末に
「最適化」されたものを組みこめると、
さらに理想的です。
No.10
クローズアクティビティを作ろう
首尾よくコースを終了するための
テンプレート的な
締めの挨拶を作りましょう。
おすすめは
最終的な要約や評価を組み込むことです。
これにより
受講者は
学習したことを
振り返るよう誘導され
コースから何を得ているのかを認識できるようになります。
いかがでしたか?
今回ご紹介した10個のコツを
これからの“オンライン教育方針”に
組み込めば、
受講者の支援コミュニティを確保できるだけではなく、
あなたの作業自体も
最終的に容易になること間違い無しです!
とはいえ、
オンライン学習自体が
最近急速に成長してはいるものの、
いまだ構築段階にあるため
この原則も日々新たな原則に書き換わっていく事でしょう。
我々Zporta.も
常に最新で最も効果的な情報を
お伝えできるよう、努力してまいります。
些細な事でもかまいません。
あらたな情報や、ご自身で心掛けていること、
こんな記事書いてほしい!などのリクエストなどありましたら
ご気軽にコメント または メールをお待ちしております。
Zporta. は
あなたの「理想の働き方を現実にする」為、全力でお手伝いします。
次回は
「成功するフリーランサーの鉄則ルーティン 9選」を
ご紹介いたします。
楽しみにしていてくださいね!